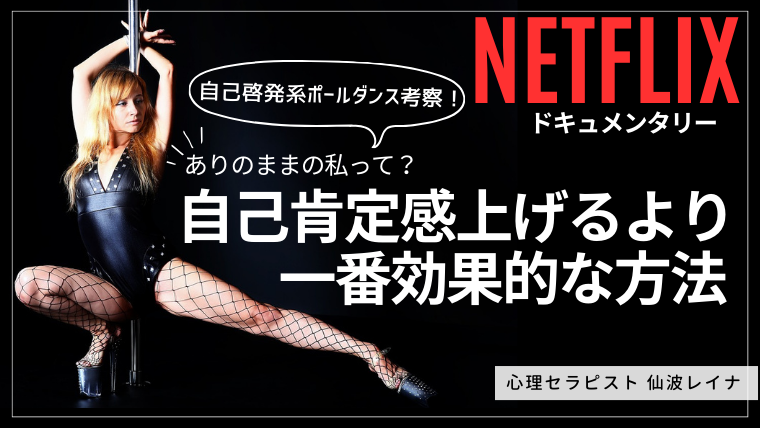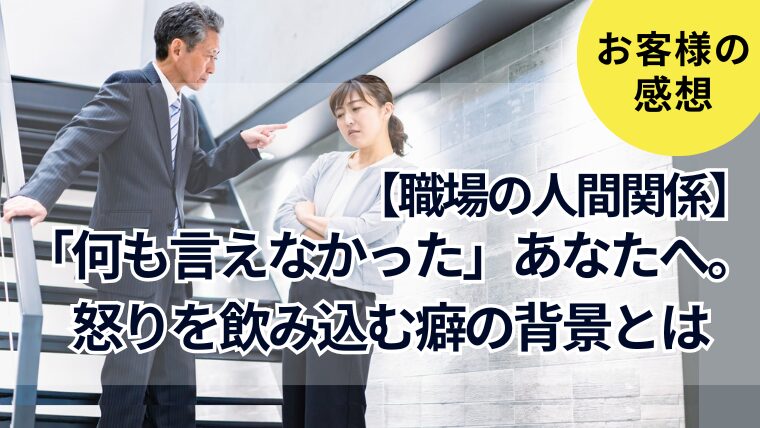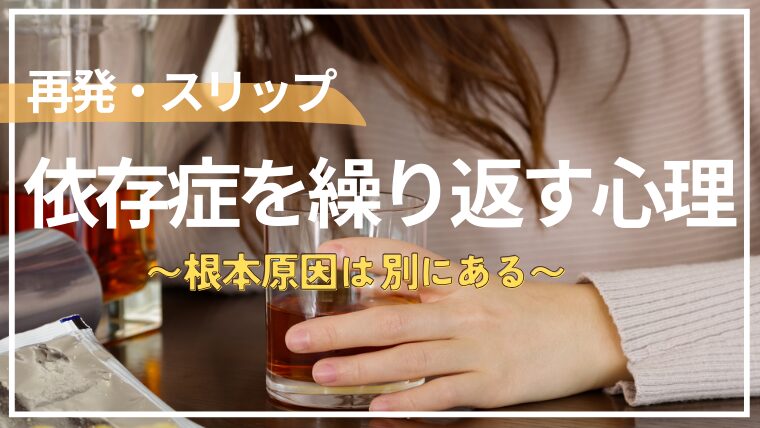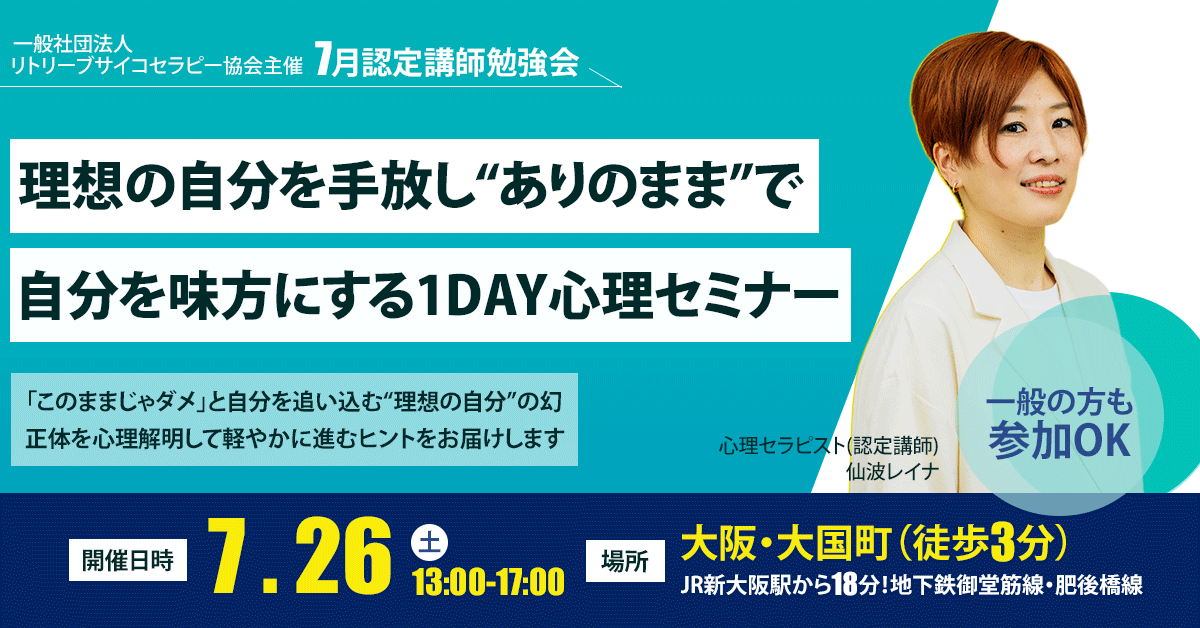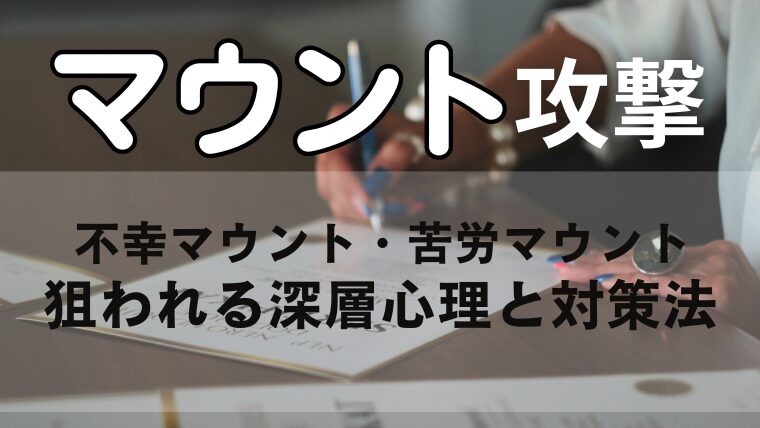【管理職必見】部下の指導疲れの心理的要因とは?原因と対策を解説!
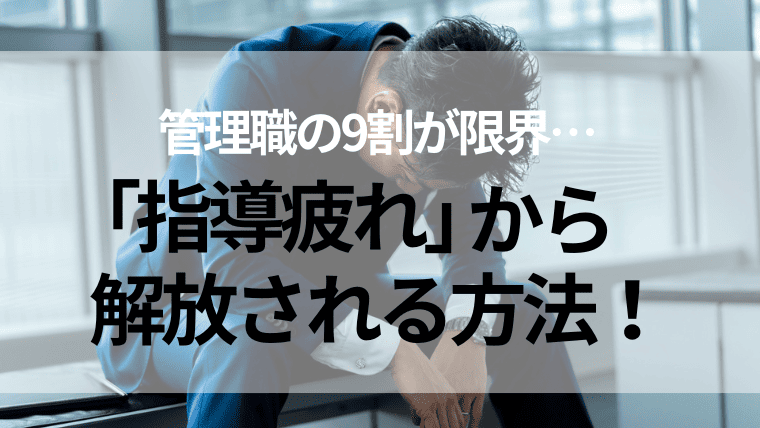
管理職を悩ます部下をどうにかしたい
管理職やリーダーとして部下を指導するのは重要な役割ですが、
「指導に疲れた…」と感じることはありませんか?
- 言うことを聞いてくれない部下
- 無視ししたり仕事をサボる部下
- 思考停止している部下
- 反抗してくる部下
指導疲れが続くと、
モチベーションの低下やストレスの蓄積につながり、
うつやノイローゼなどに繋がったり
自分だけが頑張りすぎて
最悪の場合、燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥る可能性もあります。
本記事では、部下の指導疲れの主な心理的要因と、
その対策について詳しく解説します。
今までのコーチングや自己啓発のような
相手・他人に意識した解決法とは全く違います。
あなたの「指導疲れ」までになった心理的要因を紐解くことで
本当の解決方法につながっています。
自分に向き合うと結果「人との関わり方」が変わり
仕事や職場も影響を受けて変化していきます。
結果、あなたの仕事の負担を軽減しながら
気持ちよく仕事ができるようになるヒントをお伝えしますので、
ぜひ最後までご覧ください。
指導疲れの心理的要因は自分の中にある
指導疲れについては変わらない相手や管理する組織・会社側にも
もちろん責任ががあります。
ですが、心理セラピーでは下記の視点を大事にします。
「過去と他人は変えられない、未来と自分は変えられる」
選択理論心理学 byアメリカ精神科医ウィリアム・グラッサー博士
「他人と過去は変えられない」
自分が自分を変えられるということは
「今の現状を自分が選んでいる」という真実、
今は信じられないかもしれませんが「この視点があるんだな」
とピン留めしながら読み進めてくださいね。
ますは指導が疲弊するまでになっているときに
自分の中で心理的に何が起こっているかを確認していきます。
1. 期待通りに動いてくれないストレス
部下に対する指導で最も大きなストレスのひとつが、
「期待通りに動いてくれない」ことです。
- 期待が大きいほど失望も大きい
「これくらいできて当然」「成長してほしい」という期待が大きいと、それに応えられない部下を見て苛立ちや落胆を感じてしまいます。 - 管理職自身の成功体験とのギャップ
「自分が新人の頃はもっと頑張っていたのに…」という思いが、
部下への不満を増幅させることもあります。
しかし、部下は管理職と同じ価値観やスキルを持っているわけではありません。
「相手に変わってほしい」「相手が変わるべきだ」
誰もが感じるものなのですが、この気持ちが強い場合に苦しみます。
「他人と過去は変えられない」これは絶対真理です。
もちろん、自分の指導で変わる部下もいます。
ですがそれは結果、「自分で変わろう」と相手が決めたから起こったこと。
どんなに指導育成スキルがあっても
全員変えることは不可能な残念な現状があります。
「相手は自分とは違う」と受け入れることができない状況になっています。
心理的境界線(バウンダリー)
相手と自分と心理的な境界線のこと。
適切な境界線が引けている場合、
相手の感情・責任・問題、相手がやるべき課題を切り分けられます。
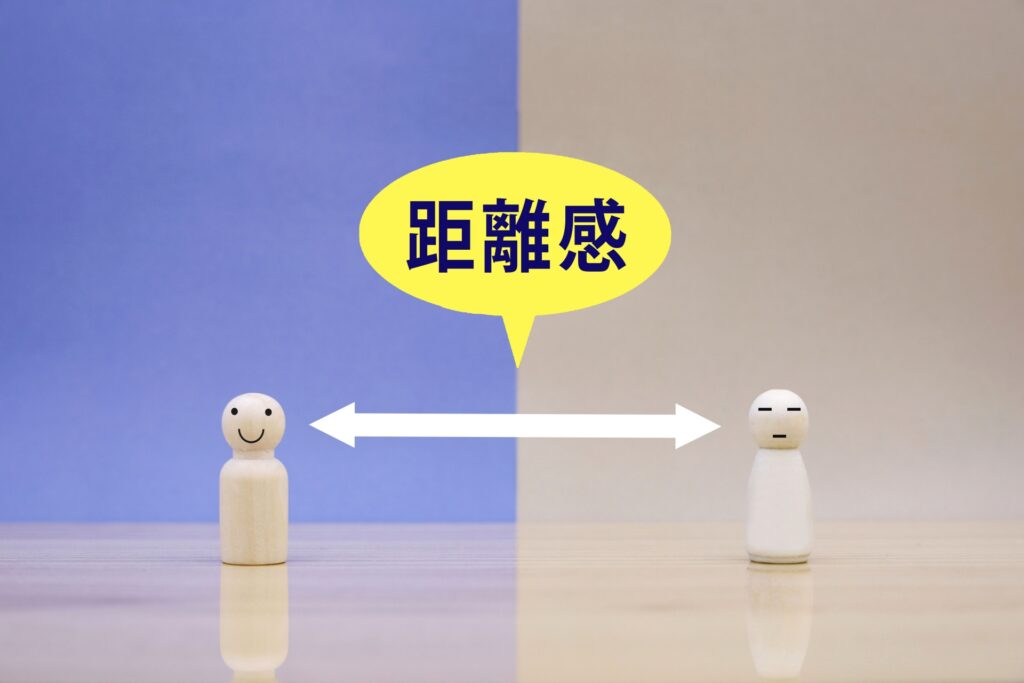
これは心理的に説明すると心理的境界線が引けていないため
相手の感情に寄り添いすぎたて自分の感情の一部になっていたり、
相手の責任を自分の責任まで感じて背負い込んだり
相手のやるべき課題を自分が片付けてしまいます。
境界線がない状態とは「無境界」と呼ばれます。
実は、相手ではなく自分が相手の境界線に踏み込んでいます。
「相手が変わってほしい」
だからなんとか変えようとするがあまり
結果、わざわざ疲弊することを自分が選んでいます。
衝撃の真実に多くのクライアントがショックを受けます。
2. 責任感の重さによるプレッシャー
管理職は、組織の成果に責任を持つ立場です。
しかし、その責任を「すべて自分が負わなければならない」
と感じてしまうと、過剰なプレッシャーが生じます。
- 責任は管理職だけのものではない
確かに管理職の責任は大きいですが、社員の職務怠慢やミスに対する責任は雇用契約上は本人自身、雇用している会社や組織にもあります。 - 「すべて自分の責任」と思い込むことでストレス増大
責任感が強い人ほど、部下の失敗を「自分の指導不足のせいだ」と思い込みがちです。自分に矢印を向けて「罪悪感」や「自己嫌悪」に陥ります。
しかし、管理職の役割は「適切に部下を導くこと」であり、
「すべての責任を一人で抱え込むこと」ではありません。
3. 感情労働によるストレス
仕事には、大きく分けて肉体労働・頭脳労働・感情労働の3つがあります。
管理職が直面する指導疲れの多くは、この「感情労働」によるものが大きいです。
感情労働とは?
感情労働とは、自分の感情を抑え、相手に合わせて適切な態度を取り続けることで
成り立つ労働のことです。具体的な職業としては、下記の通りです。
1. 接客・販売業
例:飲食店スタッフ、ホテルスタッフ、ショップ店員、カスタマーサポート
2. 医療・介護職
例:看護師、介護士、医師、歯科助手
患者やその家族の感情に寄り添いながら対応する必要があり、精神的負担が大きい。
3. 教育・保育職
例:教師、塾講師、保育士
子どもや生徒、保護者との関係構築が重要で、感情のコントロールが必要。
4. コールセンター・カスタマーサポート
例:電話オペレーター、問い合わせ窓口
クレーム処理が多く、理不尽な要求にも冷静に対応しなければならない。
常に笑顔で丁寧な対応を求められ、ストレスが蓄積されやすい。
5. 福祉・ソーシャルワーク・対人援助職
例:ソーシャルワーカー、心理カウンセラー、ケースワーカー
クライアントの悩みや問題に深く寄り添う必要があり、精神的に疲弊しやすい。
6. 管理職・マネージャー職
例:企業の管理職、人事担当者
部下の指導や人間関係の調整が求められ、自分の感情を抑える場面が多い。
7. 公務員(対人業務)
例:市役所の窓口職員、警察官、消防士
市民対応や危機的状況に対する対応が求められ、精神的なプレッシャーが大きい。
【指導疲れ・支援疲れ】なぜストレスがかかるのか?
感情労働の負担を軽減するには、
適度な距離を保つ、自己ケアを意識する、相談できる環境を作ることが
現実的解決策として大切とよくいわれていますが
「指導疲れ」「寄り添い疲れ」「支援疲れ」の人たちは、その真逆の心理状態です。
- 心理的境界線が引けていないこと
- 自己ケアよりも他人のケアを優先してしまう
- 相手の相談に乗るばかりで自分に相談できる環境や人に助けを求めるのが苦手
人に頼れない甘えられない - 自分で全ての責任を背負いこむ傾向がある
この心理状態が無意識にある場合、いくら環境を整えても根本から解決にはなりません。
無意識に責任を背負い込み一人で仕事を抱えて、
気がつけば人の世話や面倒を見すぎています。無意識にしているので気づけません。
人に頼ることもできません。
これは職業柄でなく、
幼少期まで遡ると両親との関係や家庭環境で染みついた心理的特徴です。
これが心理的要因となり「指導疲れ」を引き起こしています。
感情労働では、本音を抑えて建前で対応することが求められるため、
精神的な負担が蓄積されます。
特に、部下、患者、お客様、しいては家族のために
自分の感情を抑え込み気を遣いすぎることを習慣化し、
心身ともに疲弊してしまいます。
指導疲れ・支援疲れの原因は「寄り添い疲れ」
「指導疲れ」「支援疲れ」は、
「仕事が大変だから」「職業柄そうならざるを得ない」だけが理由ではありません。
実は、その根本的な原因は、
その人自身が心理的に抱える「寄り添い疲れ」にあります。
- 人に対して自分の感情や欲求を抑圧してしまう
- 相手の気持ちを考えすぎて、必要以上に寄り添いすぎる
- 仕事だけでなく、プライベートでも同じような関わり方をしている

つまり、「仕事・業種だから仕方ない」のではなく、
元々の人間関係のパターンとして
「人の感情に寄り添いすぎる癖」があるんです。
5. 「寄り添わなければならない」不安と恐怖
なぜここまで疲弊してまで人に寄り添おうとするのか?
「人に寄り添いたい」気持ちを超えて
「人に寄り添わなければならない」という責任感、義務感や強迫観念が強くあります。
深く掘り下げていくとその根底には、
「寄り添わなければ」起こってしまうことを無意識に想像して感じる
不安や恐怖が隠れています。
クライアントの多くにある例として以下の通りです。
- 「人の期待に応えないと、見捨てられるかもしれない」
(見捨てられる・居場所がなくなる恐怖) - 「役に立たなければ、自分には価値がない」
(無価値感・自分は生きている意味がない生存の恐怖) - 「他人の感情を優先しないと、人間関係がうまくいかない」
(自分の感情や欲求を抑圧・殺さなければ受け入れてもらえない恐怖)
潜在的に持っている不安や恐怖は人それぞれいろんな形があります。
人は不快な感覚を避けたり、不安を埋めるような行動に出ます。
快感原則
人は「不快(不安・恐怖)」を避けて「快(快感)」を得る
by心理学者・精神科医ジークムント・フロイト
これらの不安や恐怖が過剰に大きすぎる場合、
無意識に過剰な行動を促してしまいます。
人は無意識に不安や恐怖で想像をしてしまい、不安を埋める行動に出るからです。
なぜ気づかないのか?
「無意識」の世界は普段日常の「顕在意識」では気づかない領域です。
また、最初の動機は「人の役に立ちたい」純粋な動機のため
そこにまさか自分の不安や恐怖が入り混じっているとは誰も気づかないのが当然です。
【幼少期】寄り添い癖の人たちの生き方が原因
人との関わり方は、幼少期の無意識の学習によるものです。
職業や役職に就くもっと以前に備わった「人との関わり方」「生き方」が
人に寄り添うようになった原体験があります。
幼少期に形成される「無意識の関わり方」
人は、「人との関わり方」や「自分の扱い方」を、幼少期に学びます。
- 生まれてから6歳頃までに無意識のパターンが形成・確定される
- 6歳以降はそのパターンが繰り返し強化され、大人になっても変わらない
たとえば、幼少期に「親の期待に応えないと愛されない」と感じた経験がある人は、
大人になっても「周囲の期待に応えなければならない」と
無意識に思い込んでしまいます。
幼少期の原体験「両親・家族の世話をする役割」
責任感ある役職や対人援助職、支援職、接客業をしているクライアントの
多くに幼少期に共通した不安・恐怖を感じた原体験があります。
- 親や兄弟の世話をしてきた(親子逆転)
例)親の借金返済、依存症や病気の親の介抱、
兄弟の世話を親代わりにしていた
きょうだいじ・ヤングケアラー
女だからと飯炊き・家事役をさせられた(男尊女卑) - 家庭の平和や調和を保っていた
例)長男・長女として一家を背負っていた
家族のトラブルの問題解決をしていた
父の不在で父親代わりになっていた - 両親の仲裁役をしていた
例)母親の愚痴の聞き役、喧嘩の仲裁役 - 両親からの暴力を受けていた
例)ネグレクト、暴力、言葉の暴力や無視

共通してある生き方・関わり方
「自分をおざなりにして両親・家族のお世話をしてきた」
「自分の感情や欲求を抑圧して、相手を優先してきた」
子どもは両親よりも無条件に両親を
一生懸命に愛そうとします。両親のために家族を守ろうとします。
本来は大人である両親が無力の子どもを守り
愛を与えるべきなんですが
残念ながら大人が親として機能していない
「機能不全家族」の場合、
子どもは愛されたいために頑張ってしまいます。
そうしなければ、
「見てもらえない」「かまってもらえない」
「ここにおいてもらえない」
「愛されない」という生き死にに関わる恐怖を感じるからです。
その無意識が反復強化して
大人になっても同じような行動をします。
「部下だけでなく上司や会社の期待に応えなければならない」
「妻やこどものために」
「主人のために」
「家族のために」
見えないプレッシャーに駆り立てられて
結果自分を疲弊するまで追い込んでしまいます。
普段日常ではこのように言語化されていないのでわかりません。
無意識下にこのような不安・恐怖があるために、
必要以上に相手や相手の感情に寄り添い、自分の感情を犠牲にしてしまいます。
「寄り添いすぎ」を選ぶ心理的メリット
こんなに苦しい状況を自分が選ぶはずがない。
そう思っている人もいると思います。
ですが同じパターンを繰り返していたり、
自分は苦しんでいる一方で、
境界線をきちんと引いて無理なく
仕事をしている上司がいる現実はあります。
自ら選んでいる理由は、「不安・恐怖を避ける」以外に他にもあります。
子どもは家庭内での「役割」を無意識に引き受けることで
「そのときだけは見てもらえた」
「頑張ればかまってもらえた」
「自分さえ我慢すればみんな笑顔になってくれた」
「言うことさえ聞けば居場所が与えられた」

そのときだけは安心感を感じたり、
親が自分に振り向いてくれた。
本来、愛は無条件にもらえるものですが、
無条件にもらえなかった家庭で育つと
「自分がお世話をすれば〜」
「自分が役に立てば〜」
「愛は条件付きでもらえるもの」として解釈してしまいます。
「自分は無条件に愛されない」”前提・信念”となり
「お世話して役に立たなければ愛されない」
「もっと頑張らなければここにいてはいけない」
と言う”価値観”が形成されます。
一方で無条件で愛されない現実が
埋まらない愛情欠乏感や寂しさや孤独感を増していきます。
それを埋めるために
「役に立つこと」を選ぶ
「お世話役」に徹すること選ぶ
「みんなの責任」を一人で背負い込む
自ら選んでいる「心理的メリット」です。
この関わり方がやめられないのは
最悪のバッドエンディング「愛されない現実」の悲しみや絶望である
不安や恐怖を避けられているだけでなく、
引き換えに得ている「心理的メリット」を
自ら選んでいることに
気づかなければやめられません。
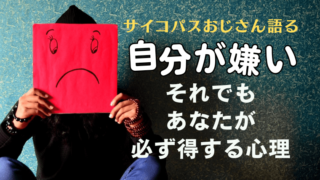
ですがこのメリットを手放せば
「私は愛されなかった」現実の悲しみや絶望感を感じてしまうので
深く眠る辛い感情や感覚を見ないで済むわけです。
そして見てもらえた感覚があるからこそ
「相手への期待」が強くなります。
期待は相手を変えようとして働きます。
変わらない・変えられない相手を見ると
期待でより一層葛藤します。
心理的メリットは「(心理的な)痛み」を避けるための
”心の痛み止め”のような役割をしています。
ですが、本当は痛みに気づいているからこそ
無意識に避けているのが悲しい現実です。
そしてその痛みや不安・恐怖があり続ける限り
やってもやっても埋まらず、
過剰に「お世話をしてしまう」ことにつながっています。
心理的境界線をわかっていない両親のもとで育ち
親兄弟のためにしてきたため
自分と親との境界線の「無境界」になっていて
家族を守ることと役に立たなければ愛されないプレッシャーが
過剰な責任感や義務感となり
自分だけで他人の感情、責任や問題まで背負いこむ
「両親・家族との関わり方」が大人になっても再演されます。
不安や恐怖、
本当は子どもの頃から傷ついてる心(無意識)が根本問題であり
向き合い癒すことが先決です。
7. おわりに
指導疲れの原因は、単なる「業務負担過多」だけではない
それを一人で抱えて頑張ることを自ら選んでいる事実から
別の心理的理由があります。
業務過多や部下や組織の責任まで背負い期待に応えるのは
過去の生き方「寄り添いすぎる人との関わり方」にあります。
「お世話をしたきたこと」
「責任を背負ってきたこと」
これが生きてきて得意だからこそ、
支援職や対人援助職、福祉・医療従事職、
責任ある役職についている人が実はとっても多いんです。
あなたの不安・恐怖や
深く抱えている心の傷に向き合うことで
無理ない仕事の関わり方・指導・支援も選ぶことができます。
心理面を癒すことができたとき、
心理的境界線が自然に引かれて
自分自身の感情を大切にすることができ
結果、指導の精神的負担を軽減し、
より健全なマネジメントができるようになります。
管理職としての役割を無理なく果たしながら、
自分自身も無理なく働ける環境を目指せます。
「変えられるのは自分」この本当の意味は
「心理的メリット」を選んでいる自分だったと言うことは
自分で選んでいることがわかれば、やめることも選択できます。
「やめてどうやって人と関わりたいか?」も選ぶことができます。
注意しておくと、「あなたに責任がある」と責めていません。
誰しもしているから安心してください。
「傷ついた自分を守る唯一の術だったんだ」と
自己理解としてまずは受け止めてあげてくださいね。
自分の人生をよりよくするために
心理セラピーであなたのお悩みを根本解決できるのを
サポートしています。